前田裕幸氏が解説!建設会社の特徴について
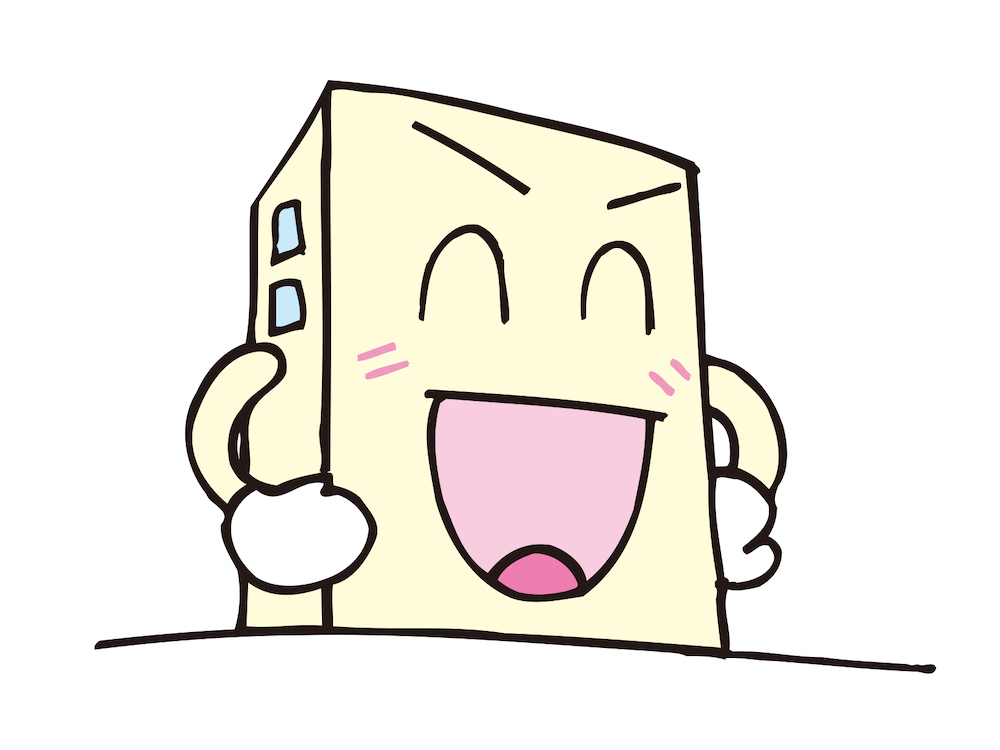
1,大手建設会社「ゼネコン」とは…
建設会社とは要するに住宅、商業施設、工場、あるいは道路やダム、港湾施設などに至るまで、さまざまなものを建設する仕事をしている会社ということになります。
たったこれだけの説明からでも分かるとおり、そのカバーする範囲は非常に広くなっており、どんなに大きな会社であっても1社で全てをカバーするようなことはできません。
大企業であれ、あるいは中小企業であれ、それぞれに得意分野を持っていて、互いにつながりを持ちながら仕事をしています。
※参考・・・前田裕幸代表~株式会社プロネオを導いてきた実力とは?
大企業とは即ちゼネコンと呼ばれるような会社を指します。
ゼネラルコンストラクターの略であり、日本語で言えば総合建設業とでもいったような意味になります。
総合建設業であればどんな種類の建物、施設であっても絶てる能力を持っているのではないかと思われるかもしれませんが実際には決してそうではありません。
というか、むしろゼネコンの社員が実際に建物を建てる仕事をするようなことはまずないのが現実です。
実際に建物を建てる仕事は下請け会社が行っていることが普通だからです。
ではゼネコンは一体何をしているのかと言えば、簡単にいうと管理監督の業務です。
どの下請け会社にどの仕事を回すかを考えて決めたり、実際に割り振った仕事が予定どおりきちんと進んでいるのかどうかの確認をしたりしているわけです。
ですから、ゼネコンの社員の仕事のほとんどは、イメージ的に言えばスーツを着て空調の効いたオフィス内で行っている事務作業です。
ヘルメットをかぶり、作業着を着て建設現場で肉体労働をしているようなイメージからはほど遠いものです。
もちろん、いわゆる現場監督と呼ばれる仕事もあり、これはゼネコンの社員が担当していることも多いですから、作業着を着て建設現場にいるゼネコンの社員は全くいないというわけではありません。
ですが、作業着を着ていたとしてもこの人は監督ですから、あくまでも工事の進捗状況や作業員たちの労働状況を管理監督するのが仕事であって、実際の建設作業を行うわけではありません。
2,建設業界のシステム
建設会社の別の特徴として、下請け会社は直接ゼネコンから仕事をもらっているのかというとそうとも限らないということが挙げられます。
つまり、ゼネコンから直接仕事を請け負う一次下請けがあり、一次下請けから仕事を請け負う二府下請けがあるというように重層的な構造になっているのです。
大規模な建設工事、例えば国際空港を建設するとか、超高層ビルを建設するといったようなものになると、四次とか五次くらいまで下請けが存在することも十分にあります。
もちろん、ある会社が何次の下請けになるかというのは、その会社の規模や実力などによってだいたいの目安というのは存在しているものの、完全に固定されてしまっているわけではありません。
ある仕事では一次下請けの会社でも、別の仕事では二次下請けになることもありますし、その逆もまた然りです。
簡単に想像がつくように、下請けが進めば進むほど、中間マージンが取られる分だけ収入は少なくなってしまいます。
その意味では、同じ下請けであってもできるだけ上の階層で仕事を受けることができるに越したことはありません。
ですが、そもそもどうしてこんなに重層的な下請け構造が必要になるのかということの答えの一つが、先にも書いたようにどんな会社であっても建設に関わる仕事の全てをこなすことはできないという現実があります。
3,建設会社の事情
能力的に言っても、また抱えている作業員の絶対数から言っても、本当ならば上から請け負った仕事を全て自社でこなせるに越したことはなくてもそれが不可能という事情があるわけで、ある意味でやむを得ないということです。
ですから、建設会社で働くことは、必然的に他の会社とうまくやっていく力が重要になります。
ある意味ではライバル会社なのかもしれませんが、だからと言って常にいがみあっていてはまともに仕事が進まず、協力できるところはお互いが進んで協力しないといけないという風土ができあがっています。
談合などは社会的に決して許されることではありませんが、他の産業と比較するとそれが起こりやすい土壌があると言うこともできるでしょう。
また、これは別に建設会社だけに限った話ではありませんが、景気の影響を大きく受けることも事実です。
お金がなければ、どんな人も家を建てるのは延期するかという話になるでしょうし、それは経営者がビルや工場を建てる場合であっても、あるいは国が税金でダムや高速道路を建設する場合であっても基本的に変わるところはありません。
幸いにして東京オリンピックまでは特に首都圏においては堅調に推移しているという話もありますが、オリンピックが終わればその先はどうなるのか不安を抱えていることも間違いないでしょう。
日本は少子高齢化が進んでいることも、景気がいまいちぱっとしないことと並んで不安要素ではあります。
ですが、いつの時代であっても地図に残る仕事に憧れを感じる人は多いのです。
最終更新日 2025年12月24日 by chaco2











